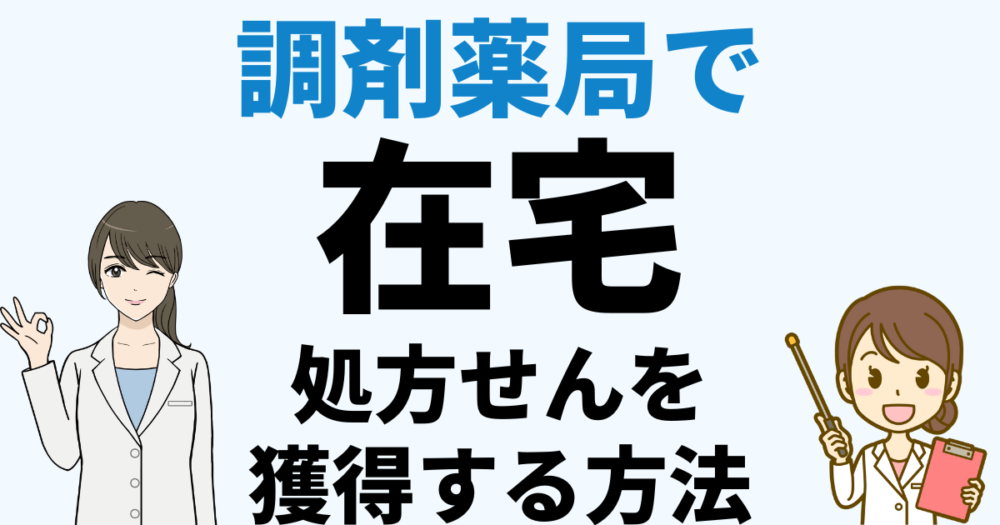- 在宅をやらないと地域支援体制加算が算定できないのでどうにかしたい。
- 在宅に取り組みたいけど依頼がこない。
- 在宅を始めたいけど始める方法を知りたい。
[char no=”8″ char=”pharma”]普段の業務にちょっと加えるだけで在宅の依頼がきます。
本記事の内容 この記事を読むと次のことがわかります。自己紹介
Follow @pharma_di Instagramのフォローもお願いします! ストーリーズでは内容の濃い情報を発信中≫ ファマディー
全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
pharma_di(ファマディー)
【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト】
面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
結論 何もせずに待っているだけでは在宅の処方せんはまず来ません。 在宅の処方せんを獲得するための行動が必要です。
在宅医療は薬局でやっている業務の延長です。薬局で服薬指導ができる薬剤師なら在宅をすることは難しいことではありません。 在宅をやるとかやらないとか言っている場合ではなく、薬局として在宅の実施は義務。 在宅の処方せんを応需して経験を積んでいきましょう。 ≫儲かる調剤薬局の作り方 ≫【薬局の処方せん枚数・受付回数】増やすために今すぐできる12の方法目次
在宅(訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導)の処方せんを獲得するための7つの方法
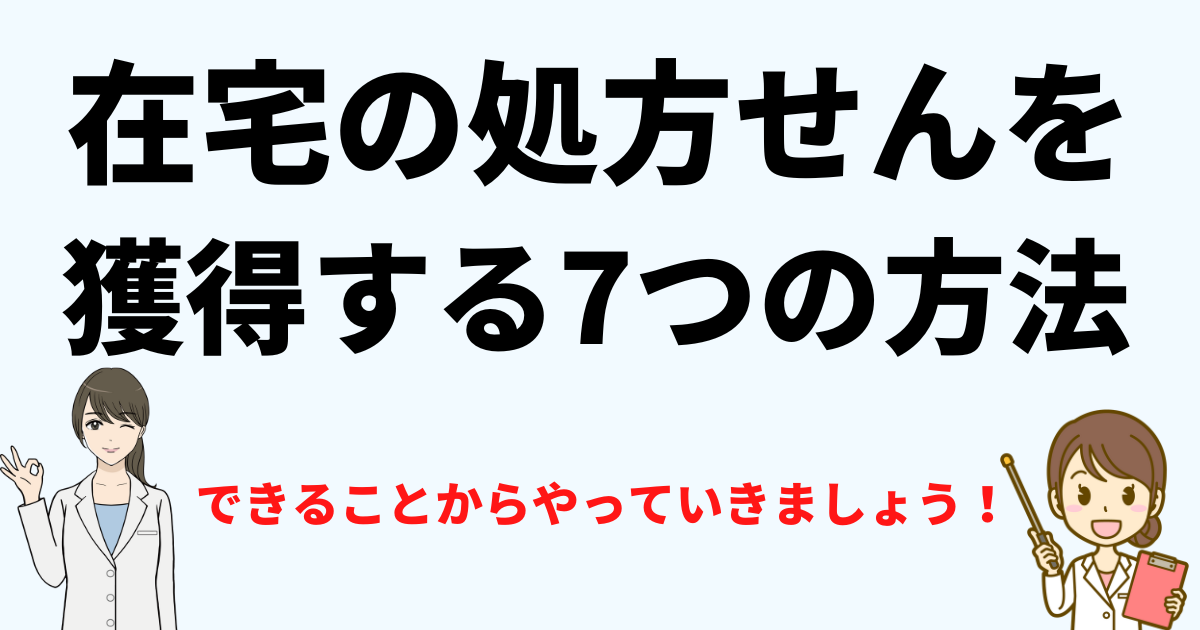 在宅の処方せんを獲得するための7つの方法
在宅の処方せんを獲得するための7つの方法- 在宅応需可能であることをアピールする
- 往診している医療機関に挨拶に行き、近くに患者さんがいたらぜひうちにと伝えておく
- 地域のケアマネさんと連絡を取り、在宅可能であることをアピールする
- 地域包括支援センターに訪問し、連絡を密にとる
- 薬局に来ている患者さんで在宅が必要そうな人をピックアップし、担当のケアマネさんや主治医に提案する
- 近隣に有料老人ホームができるという話を聞いたら即営業をかける
- 近所にお住まいの方の面処方せんを増やしておく
在宅応需可能であることをアピールする
薬情に申し訳なさそうに「当薬局は在宅医療に取り組んでいます」と書いておいても在宅の処方せん応需につながりません。 算定要件のために記載をすることも薬局の入り口の掲示することも必要ですが、それだけでは不足です。 [char no=”8″ char=”pharma”]薬情や入り口の掲示をみて、在宅お願いしたいんですけどと言われることはありません。 在宅の処方せんがゼロの時には、『こんなことを書いて在宅の処方せんが来たら困るなー』と思っていましたが、そのような心配は無用です。 待っているだけでは在宅の依頼は来ません。 まずは患者さん向けに、『薬剤師が家に行って薬の整理などできますよ』ということをアピールしましょう。 薬局のWEBサイトや薬剤師会作成の薬局リストに在宅を積極的に受けていることを記載してもらいましょう。 往診医やケアマネジャーは薬剤師会の薬局リストを参考にして在宅を受けてくれる薬局を探すことがあります。 リストに薬局が掲載されていれば在宅の依頼が来る可能性が高まります。往診している医療機関に挨拶に行き、近くに患者さんがいたらぜひうちにと伝えておく
薬局周辺に往診をしている医療機関はありませんか? 在宅専門医の場合もありますし、外来と訪問診療の両方を行っている医師もいることでしょう。 医師と面会をして在宅対応が可能であることをアピールしてください。 すぐに効果が期待できるわけではありませんが、薬局の近所の患者さんが在宅に移行した場合に依頼が来るかもしれません。地域のケアマネさんと連絡を取り、在宅可能であることをアピールする
薬剤師も在宅医療に加われますということを説明しましょう。 薬剤師も訪問できることを知らないケアマネジャーが結構います。 ケアマネジャーに対する勉強会を開催するのも良いですね。- どんな患者さんに対して保険適応になるのか。
- 医師からどのような指示がくれば薬剤師が行けるのか。
- 薬剤師が訪問に来るとケアプランへの影響はあるのか。
地域包括支援センターに訪問し、連絡を密にとる
要介護の前の要支援の段階では地域包括支援センターに情報が集まります。 心配な患者さんがいたら連絡をもらえるようにしておくとその後の在宅処方せん応需につながります。薬局に来ている患者さんで在宅が必要そうな人をピックアップし、担当のケアマネさんや主治医に提案する
薬剤師の介入が必要な患者さんが実は目の前にいた。そんなこともよくある話です。 薬剤師が気づいていないだけかもしれません。 投薬カウンターでは「残っている薬はないですよ」と言っていても、実は家での薬の管理はめちゃくちゃだった。 こういう方がいるかもしれません。 こんな患者さんには薬剤師の在宅が必要かも- 受診間隔がおかしい人
- 薬が飲めていないと疑われる人
- 病状が安定していない人
- 本人は一人暮らしで、家族がいつも薬を取りに来る人
- 輸液や経管栄養剤の処方が多い
- 実は往診しているが家族が処方せんを取りに来ている
近隣に有料老人ホームができるという話を聞いたら即営業をかける
有料老人ホームには薬剤師の訪問が必要な患者様が多くいらっしゃいます。 施設によっては事前に薬局と契約してしまっているところもありますがあきらめてはいけません。 入れるチャンスがあるのかどうかも含めて一度訪問しておきましょう。近所にお住まいの方の面処方せんを増やしておく
うちの薬局の事例です。 薬局の近くにお住まいで、ちょっと離れた大病院の処方せんをうちの薬局で調剤していました。 入院することになってしまい、しばらくお会いしていませんでした。 すると、半年後に往診をしているクリニックから電話がかかってきました。 『今度うちのクリニックの医師が往診することになりました。今までそちらの薬局さんで薬をもらっていたみたいで、今後もお願いしたいと○○さんは言っています。在宅を受けてもらうことは可能ですか?』と。 自然に向こうから依頼が来るという最高の流れです。 門前の医療機関だけでなく、近所にお住まいの方の処方せんをいかに集めておくかが重要だと思った事例でした。どこの薬局も最初は在宅ゼロからのスタート
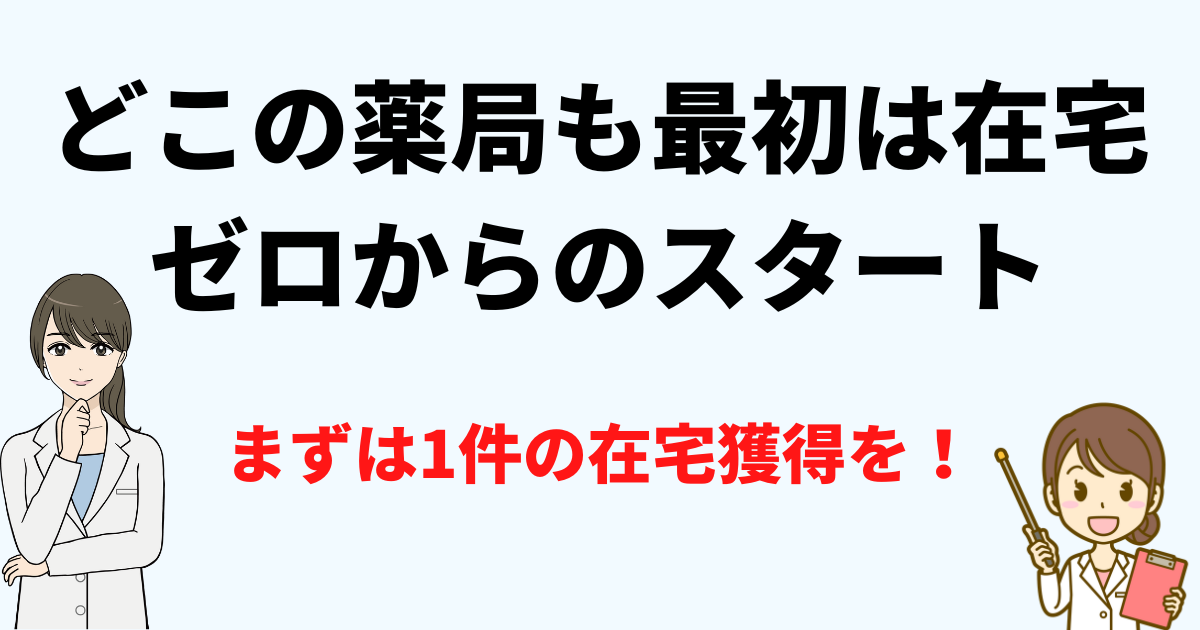 在宅の処方せんを獲得するための7つの方法を実践していくと、「在宅は受けられますか?」という電話が来るはずです。 しっかりとこの方法を実践すれば在宅の処方せんを獲得することはかんたんです。 [char no=”8″ char=”pharma”]うちの薬局は最初はゼロでした。 ですが、今では複数の医療機関の往診医から依頼が来ます。 有料老人ホームの入居者さんの訪問薬剤管理指導をすべて自薬局で対応しています。 現在では1カ月で20名の患者さんの訪問薬剤管理指導を行っています。 最初はみんなゼロからのスタートです。 在宅の依頼があったら断らないでとりあえずやってみる。 1回断ったら次はありません。 やってみるとそんなに大変ではないです。 1人薬剤師の薬局だから無理というのもわかります。 訪問日時は患者さんとの相談ですから外来の調剤が落ち着いた時間にお伺いすることも可能です。 閉局後の訪問でも良いでしょう。 話がきたらまずはやってみる。これで道が開けます。
在宅の処方せんを獲得するための7つの方法を実践していくと、「在宅は受けられますか?」という電話が来るはずです。 しっかりとこの方法を実践すれば在宅の処方せんを獲得することはかんたんです。 [char no=”8″ char=”pharma”]うちの薬局は最初はゼロでした。 ですが、今では複数の医療機関の往診医から依頼が来ます。 有料老人ホームの入居者さんの訪問薬剤管理指導をすべて自薬局で対応しています。 現在では1カ月で20名の患者さんの訪問薬剤管理指導を行っています。 最初はみんなゼロからのスタートです。 在宅の依頼があったら断らないでとりあえずやってみる。 1回断ったら次はありません。 やってみるとそんなに大変ではないです。 1人薬剤師の薬局だから無理というのもわかります。 訪問日時は患者さんとの相談ですから外来の調剤が落ち着いた時間にお伺いすることも可能です。 閉局後の訪問でも良いでしょう。 話がきたらまずはやってみる。これで道が開けます。薬局薬剤師ができる在宅の処方せんを獲得する7つの方法Q&A
Q1: 在宅の処方せんを獲得するために必要な方法は何ですか? A1: 在宅の処方せんを獲得するための方法は以下の通りです。- 在宅応需可能であることをアピールする
- 往診している医療機関に挨拶に行く
- 地域のケアマネさんと連絡を取る
- 地域包括支援センターに訪問する
- 薬局に来ている患者さんをピックアップする
- 近隣に有料老人ホームができる場合は営業をかける
- 近所の方の面処方せんを増やす
在宅経験ゼロの薬剤師は今後さらに厳しくなる
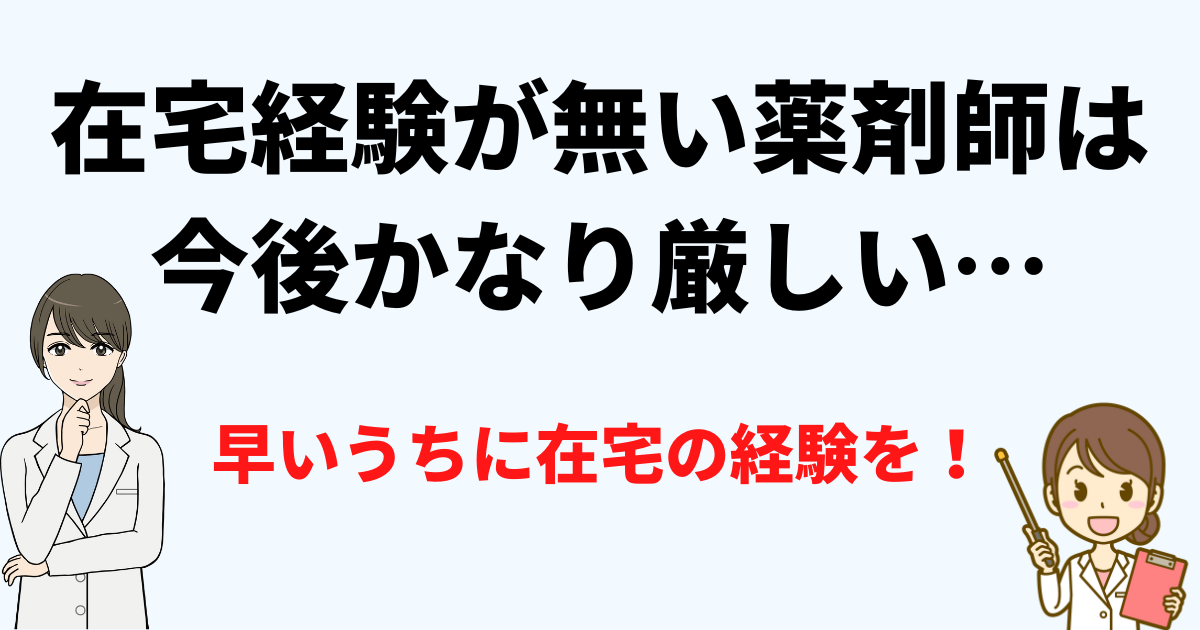 在宅ゼロの薬剤師は今後ますます厳しくなります。 早いうちに在宅の経験を積んでおきましょう。在宅ができない薬剤師は不要という時代がやってくるからです。 勤務している薬局が在宅医療に消極的であったり、依頼を断っていたりするとなかなか在宅業務を行うチャンスが回ってきません。 今現在で在宅経験ゼロは結構厳しいです。 そうならないように、今から在宅の経験を少しずつ積んでおきましょう。 在宅の経験を積めない環境で働いているなら、在宅業務ができる環境に身を置くことも考えましょう。 以下の薬剤師転職サイト・エージェントなら在宅を積極的に行っている薬局を紹介してくれます。 [cc id=40570] 調剤薬局への転職に強い転職サイト・転職エージェント4選
在宅ゼロの薬剤師は今後ますます厳しくなります。 早いうちに在宅の経験を積んでおきましょう。在宅ができない薬剤師は不要という時代がやってくるからです。 勤務している薬局が在宅医療に消極的であったり、依頼を断っていたりするとなかなか在宅業務を行うチャンスが回ってきません。 今現在で在宅経験ゼロは結構厳しいです。 そうならないように、今から在宅の経験を少しずつ積んでおきましょう。 在宅の経験を積めない環境で働いているなら、在宅業務ができる環境に身を置くことも考えましょう。 以下の薬剤師転職サイト・エージェントなら在宅を積極的に行っている薬局を紹介してくれます。 [cc id=40570] 調剤薬局への転職に強い転職サイト・転職エージェント4選- [cc id=27476]
あわせて読みたい
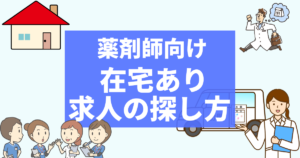
【在宅をやりたい薬剤師向け】在宅に積極的な薬局求人の探し方│メリット・デメリットも 在宅をやりたい薬剤師必見!訪問薬剤管理指導ができる薬局求人の探し方をまとめました。在宅をやりたい薬剤師はどの薬局でも欲しい人材です。在宅を経験しておくと将来大変役に立ちます。この記事を読めば在宅に積極的な薬局の探し方がわかります。