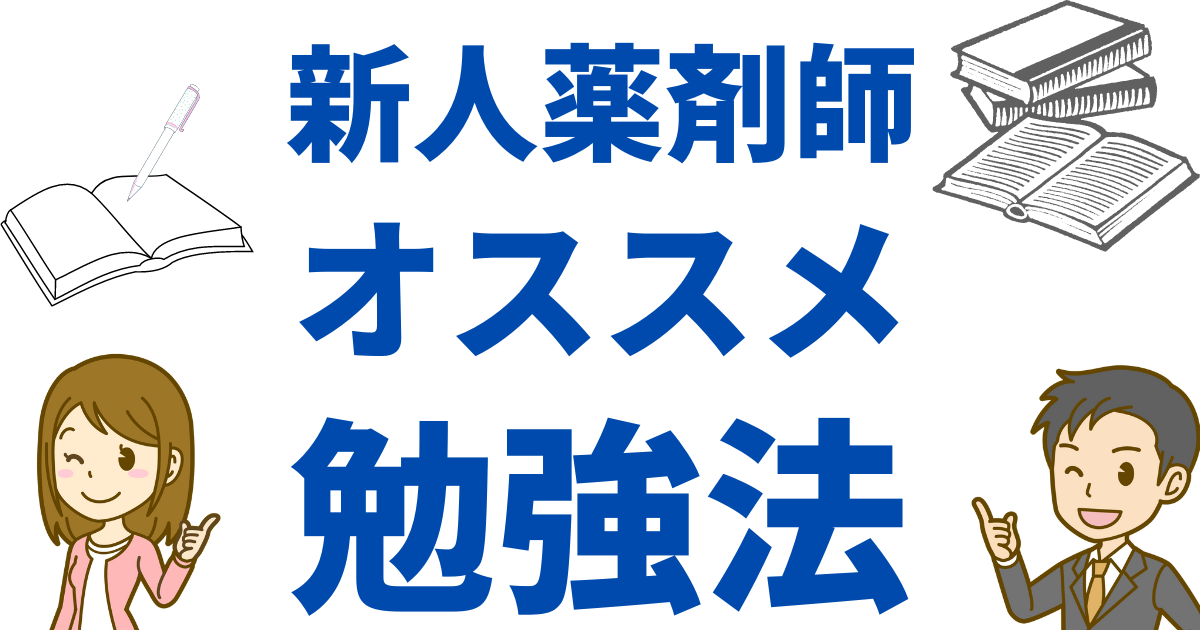勉強方法に悩む新人薬剤師
新人薬剤師はどうやって勉強していくと良いでしょうか?
何か良いアドバイスがあれば教えてください。
学生から職場に出た直後は、覚えることが雪だるまのように増えます。帰宅してそのまま寝てしまう日もあるでしょう。それでも、やり方を少し変えるだけで負担は軽くなります。私は配属初日から、「短く、確実に積み上げる」型に切り替え、仕事の出来が安定しました。ここでは、現場で明日から使えるコツに絞って紹介します。読み終える頃には、今日からの一歩がはっきりします。
Follow @pharma_di Instagramのフォローもお願いします! ストーリーズでは内容の濃い情報を発信中≫ ファマディー
全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
pharma_di(ファマディー)
【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト】
面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
職場の診療科に直結する領域に優先順位を付け、確かな情報源で「短時間×高頻度」で積み上げる。この型に変えるだけで、少ない時間でも成果が出ます。



私も配属直後は時間が取れず悩みました。必要な領域を先に決め、朝の30分で継続に切り替えたら、疑義照会や服薬指導の質が目に見えて上がりました。無理なく進めれば大丈夫です。
新卒・新人薬剤師のおすすめ勉強方法
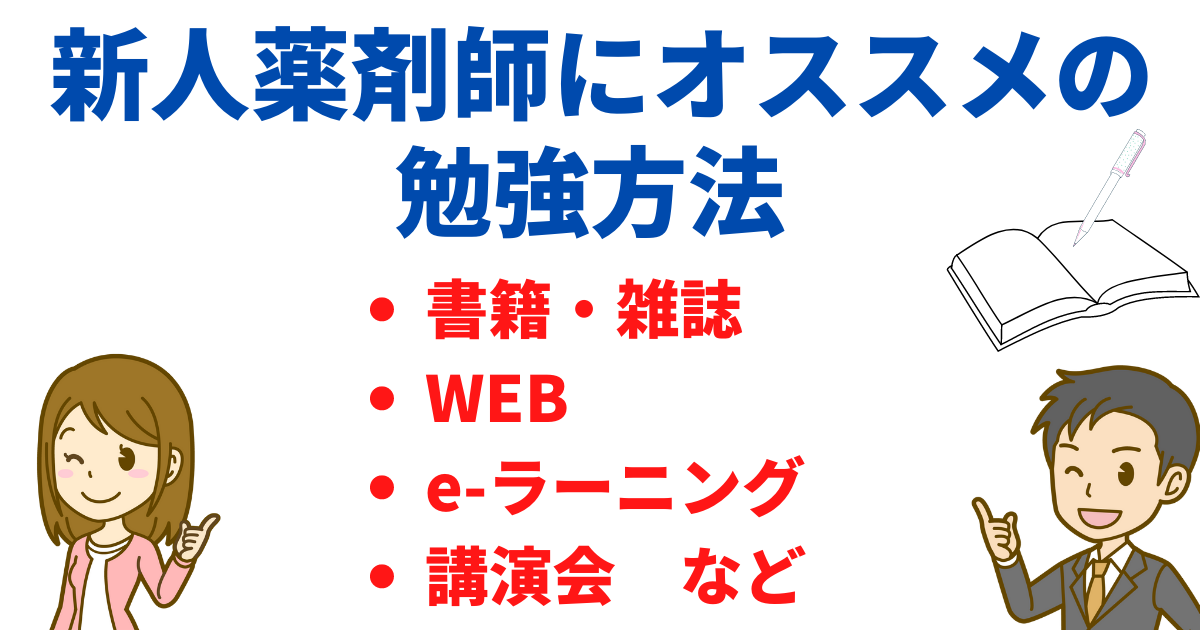
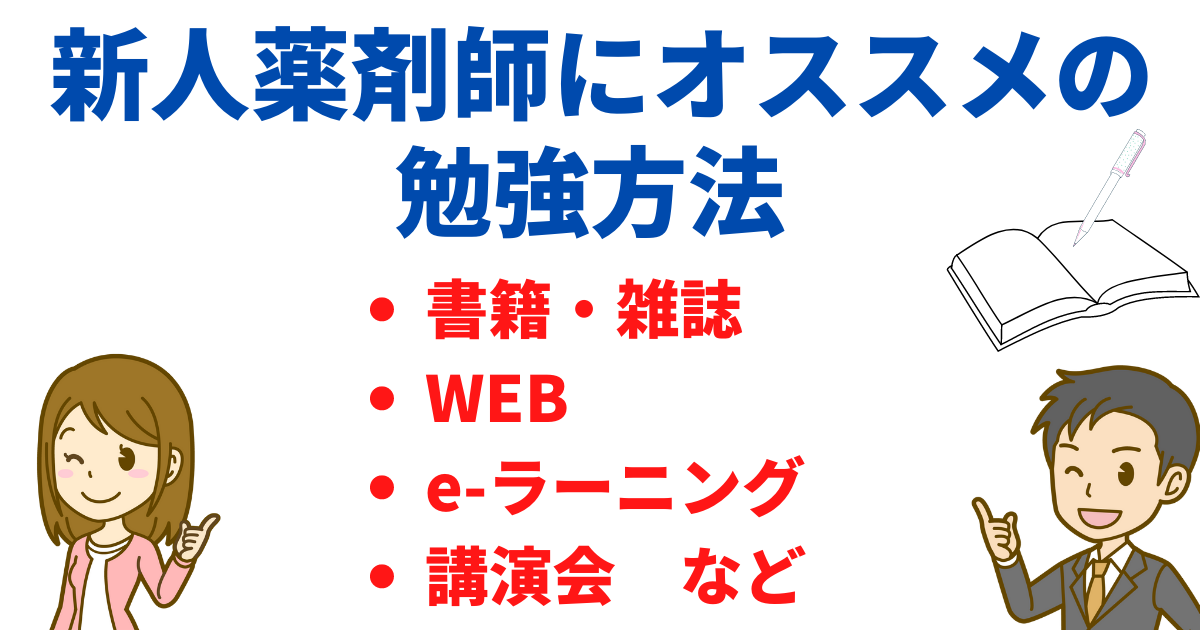
国家試験の延長では通用しません。毎年の新薬、適応追加、ガイドライン改定に追いつくには、情報の取り方を変える必要があります。ここからは、現場で使える具体的な手段を順に示します。
まずは職場で必要な知識の棚卸しから。主な診療科(内科・小児科・整形外科・眼科・耳鼻科など)を確認し、頻出薬と病態に合わせて優先順位を付けます。迷ったら先輩に素直に聞いて精度を上げましょう。
Web・インターネットで勉強する
勤務中に解けなかった疑問は、その日のうちに解決します。検索は便利ですが、情報元の確かさを必ず確認。上位表示=正解ではありません。
根拠の見方に不安がある人は、検索のコツを扱う参考書が助けになります。
信頼できる医療情報の提供元
- 薬剤師限定!日々の研鑽にはハンパない情報量のm3.comの登録が不可欠です。薬剤師の約7割が登録!
- 医療ニュースや薬剤情報を簡単入手!
- ここでしか読めない専門家のコラムも!
- 登録無料!1分で登録完了!
- 今だけ最大3,500円相当のポイントがもらえる!
- 締切は2025年12月31日!
\ここからm3.comに登録して/
アプリを使って勉強する
重い本を持ち歩かなくても、通勤や待ち時間で学べるのが利点。おすすめは下記でまとめています。
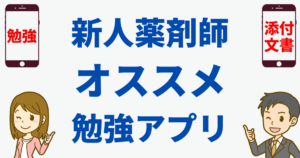
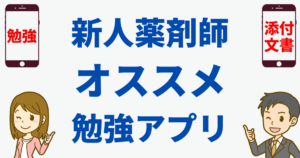
e-ラーニングで勉強する
自宅のPCやスマホで完結。認定薬剤師の単位にも対応しているものが多く、会社の補助が使える場合もあります。
本・書籍・参考書で勉強する
体系だった内容にアクセスでき、必要な章だけを繰り返す使い方ができます。分厚い本でも、今日の症例に関連する部分からで構いません。


雑誌で勉強する
定期購読なら毎号テーマが深掘りされ、偏りなくアップデートできます。忙しい時期でも届いた号から読み始めましょう。


講演会・勉強会に参加して勉強する
製薬会社・薬剤師会・自治体・医療機関などが開催。オンラインも増え、仕事後に参加しやすくなりました。案内が来たら、テーマと自分の課題の一致度で選びます。
- 製薬会社主催(医師講演)
- 薬剤師会主催(薬剤師講演)
- 市町村主催(他職種連携)
- 薬局・病院の院内勉強会
診療ガイドラインを読んで勉強する
ガイドラインは医師の治療方針の土台。読むと処方意図や重症度の見立てがクリアになります。アプリやウェブからアクセスできます。
検索例:
文献・論文を読んで勉強する
PubMedやコクラン・ライブラリー、日本語ならJ-STAGEが便利。抄録だけでも、結論と限界を押さえる習慣を付けましょう。検索の型は参考書が役立ちます。
新人薬剤師におすすめの勉強時間は朝
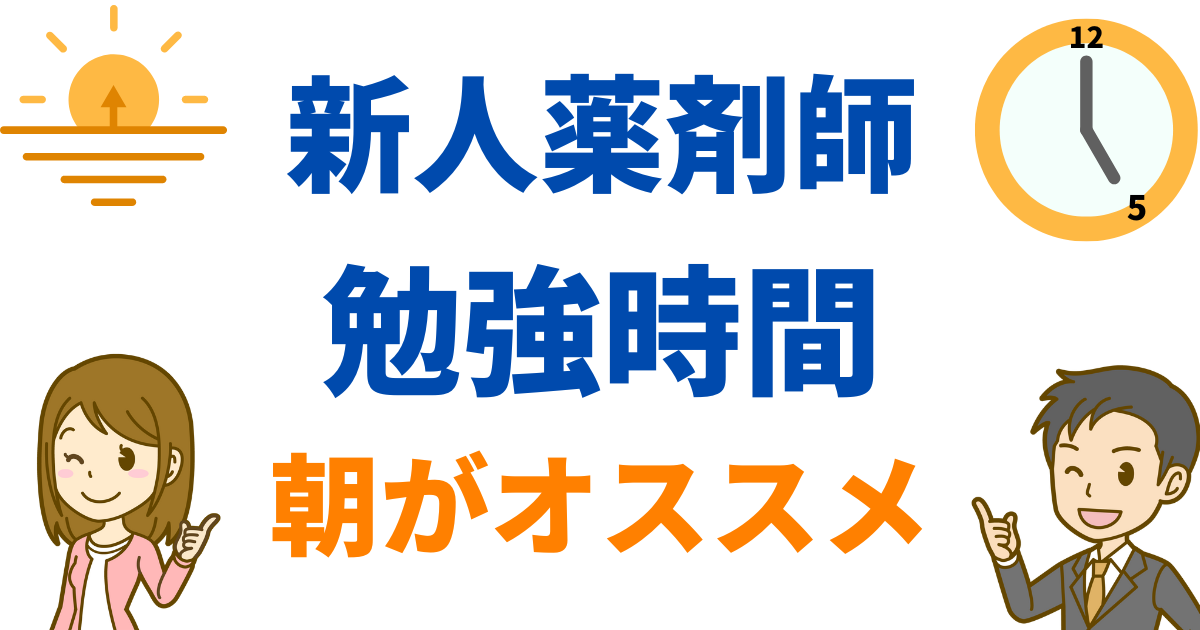
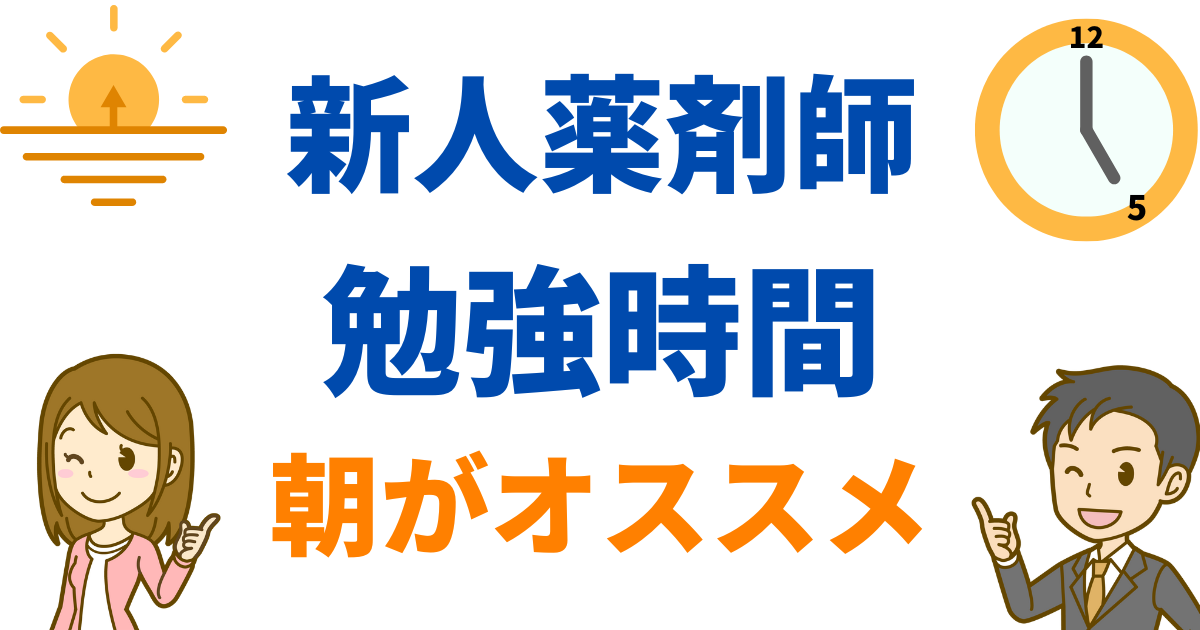
社会人はまとまった時間が取りづらいからこそ、朝の短時間が効きます。スキマも合わせて、次の時間帯を使い分けると継続しやすくなります。
- 朝(家で)
- 通勤時間
- 勤務中
- 昼休み
- 寝る前
- 休日
朝早起きして家で勉強する
脳が冴えている時間帯。アウトプット系(計算・記述・要点整理)を置くと伸びます。暗記は夜に回すと効率的です。
通勤時間に勉強する
電車・バスはテキストやアプリ、車・自転車は音声教材で。毎日の積み上げが大きな差になります。
勤務中に勉強する
本を読むのではなく実務から学ぶ時間。わからなかった薬や質問は必ずメモし、その日のうちに用法・相互作用・注意点を確認します。解けない時は先輩に相談を。
昼休みに勉強する
軽めの復習に充てます。午前の疑問を1つだけ解くなど、小さなゴールで負担を減らします。
仕事終わりに勉強する
その日のモヤモヤはその日のうちに。業務記録と一緒に3分で要点を整理し、翌日の確認事項を決めておきます。
入浴中に勉強する
音声や短文の読み物に最適。機器の濡れには注意しつつ、受け身の学習で気分転換もできます。
寝る前に勉強する
暗記・復習の時間。睡眠中に記憶が固定されやすいので、用量・禁忌・監査ポイントなどを短く回します。無理は禁物です。
休日に勉強する
平日で不足した分を補う日。場所を変えて集中したり、ガイドラインや雑誌の特集など腰を据えて読みます。
Q&A|新人薬剤師の勉強に関するよくある質問
短時間で結果を出すための疑問をまとめました。重要語は太字で示します。
Q1. 効率よく勉強する最初の一手は?
診療科と頻出薬の把握→優先順位付けです。必要なところから着手すると無駄が減ります。
Q2. 何を優先して勉強すべき?
配属先の主科の病態・標準治療・第一選択薬。次に相互作用と減量基準を押さえます。
Q3. 信頼できる情報源の見分け方は?
公的機関・学会・一次情報を優先。誰が、どの根拠で出しているかを必ず確認します。
Q4. e-ラーニングの使いどころは?
まとまった知識を系統立てて整理したい時。認定単位の取得にも向きます。
Q5. 勉強会は参加すべき?
必要なテーマなら参加を。オンライン化で参加しやすく、最新動向と実例を得られます。
Q6. 論文は英語が苦手でも読める?
抄録の目的・結果・結論だけでも十分価値があります。日本語はJ-STAGEや一部のコクランで補えます。
Q7. 朝と夜、どちらを勉強に充てる?
朝はアウトプット、夜は暗記が基本。無理なく続けられる配分に調整します。
Q8. メモはどう活用する?
その日解けなかった疑問を3件だけ記録→当日中に解決。翌日の服薬指導に直結します。
Q9. 情報が多すぎて迷う時の対処は?
患者数×重みで優先度を数値化。頻度の高い病態から順に学べば迷いません。
Q10. 継続のコツは?
時間の固定化(毎朝20〜30分)と可視化(チェック表)。小さな達成感を途切れさせない仕組みが効きます。




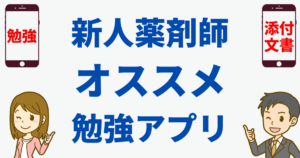
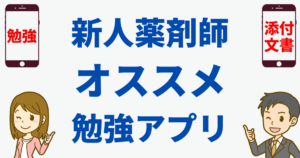
≫勉強も大事ですが、新人薬剤師のうちにマナーを身に付けておきましょう。
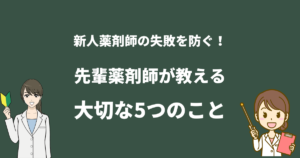
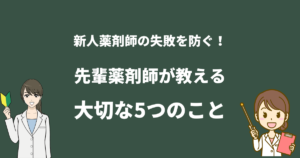
≫新人薬剤師が身に付けておきたいマナーとコミュニケーション術
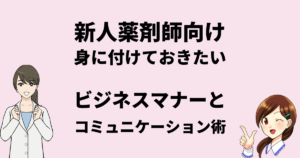
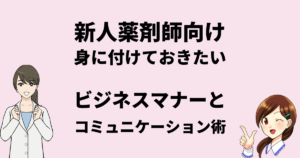
新人薬剤師の勉強法まとめ|少ない時間で成果を出すコツ
- 診療科に直結する領域から優先して学ぶ
- 信頼できる一次情報と公的サイトを軸にする
- 朝の短時間×高頻度で積み上げる
- 疑問は当日中に3件解決を目標に
- 書籍・雑誌・eラーニング・勉強会を用途別に使い分け
結論:必要なところから、短く速く。朝の30分と通勤の15分を固定し、職場の頻出領域から攻めるだけで、服薬指導の精度と監査の質は安定します。根拠は公的情報と学会資料を起点に、書籍で補強。疑問は当日に片づけ、翌日へつなげます。これが新人期の最短ルートです。
開店前の静かな時間、湯気の立つカップの横でメモを開く。昨日取りこぼした「相互作用」「用量」「減量基準」を3つだけ確認。通勤ではアプリで要点を復習し、昼に1つ検証。退勤前にその日の気づきを書き留める。この小さな往復運動が、自信と成果を連れてきます。迷ったら、優先順位を職場の先輩に当てて微調整。背伸びしすぎず、今日から30分だけ始めてみましょう。数週間後、患者さんへの言葉と手が変わります。



当サイトでおすすめしている薬剤師転職サイトはこちらです
- 正社員・パート・派遣全てお任せ
- 女性薬剤師に特におすすめ
- じっくり相談したい薬剤師におすすめ
- 薬剤師転職支援25年以上の実績!全国12拠点
\ 転職者満足度が高い! /
- 正社員・パート・派遣・単発派遣・紹介予定派遣全てお任せ
- 取引企業・医療機関7,000社以上!
- 47都道府県全ての求人取り扱いあり
\ 正社員・派遣社員ならここで決まり /
- 薬学生も登録可能!
- マッチング精度が高い!
- 職場への逆指名交渉あり!
\ 大手調剤チェーン運営で安心 /
- 正社員・パート・派遣全てお任せ
- 完全独立系だから中立な立場で紹介
- 薬剤師転職サポート25年以上の実績
\ 転職活動に少しでも不安があるなら /